| 趣味のスケートとバンクーバー・オリンピック雑言など |
| 川村 知一 |
| はじめに 退職後、少々ハードであるがアイススケートを趣味にしている。 長年悩まされた腰痛が3年間のプール通いでほぼ完治し、次のステップとして、近くのダイエー新松戸店にあったアイススケート場に通い始めた。従来のホッケー靴から6万円ほど投じて本  格的なフィギュア靴に変更した。 格的なフィギュア靴に変更した。ところが間もなくダイエーの経営難でスケート場が閉鎖になり、しばらく中断したが、明治神宮スケート場を知って、ここ3年ほどは月1,2回のペースで神宮に通っている。 昨年、製氷パイプ、場内施設などが全面的に改修され、氷上コンディションが極めて良好で、快適なスケートを楽しんでいる。(趣味の方にはお勧めである) 前段(アイススケート事始め) 戦後間もない昭和24年、私が清滝小学校2年生の時、精銅所の北の水沢地区に天然リンクができ、冬の日光では他に娯楽もなく、従業員および家族がこぞってアイススケートを楽しみ始めた。 最初はフェンスもなく、戦前から靴を持っていた人は革製のスケート靴で、新規の人は下駄スケートを買って楽しんだ。 しばらくしてフェンスが出来て、電工のアイスホッケーの練習が始まり、立教大学などが練習や親善試合にやってきた。 昭和25年には細尾に東洋一と称された外周400m天然リンクが出来、男の子はスピードスケート(ロング)靴を競ってはいた。 車などない時代、丹勢の坂を下り、清滝小学校を抜けて渇水期の大谷川を石伝いに渡り、細尾のリンクに辿りついた。灯油もガスもない時代、火の気一つないリンクで貧弱な防寒着で滑り、凍えて家に帰り着く、難行苦行のスケートであった。 中段(東京のスケート場) 昭和26年9月、小学4年生で単身上京した私が最初に連れて行ってもらったスケート場は、新宿伊勢丹2階にあった。しかし2,3回行ったのち閉鎖になり、その後は後楽園、浜松町のリンクに行った。 中学、高校ではスケートと疎遠になったが、早稲田大学に入り、商学部の学生が運営するスキー・スケート同好会という妙な同好会に入った。 夏は都内のスケートリンクで足を鍛え、冬にスキーに行くというものであった。 昭和39年(1964年)、大学3年の時、シーズンスポーツ授業としてアイススケートが抽選でとれ、下期だけであったが、早朝の池袋スケート場に70名ほどの学生の1人として参加した。 指導は早稲田のアイスホッケー部監督、小島先生と記憶する。生徒の中に1週間後にインスブルック・オリンピックに出発する福原美和選手がいた。 (インターネットで調べると、古河電工が多くのアイスホッケー選手を送り出したスコーバレー・オリンピックにも高校生で出場していた。) 後段(明治神宮スケート場) 通い始めた神宮のリンクの客層は、女子フィギュア選手から女子フィギュア選手を目指す小学校低学年の生徒(母親同伴)まで、充実したコーチ陣による個人レッスンを受け、昔の細尾リンクとは雲泥の差の環境である。 コーチ陣には、元オリンピック選手、ユニバーシアード、国体選手などが在籍し、中でも福原美和、佐野稔は毎日のように個人レッスンを行っている。 (練習の合間に、福原コーチとは、早稲田でのスケート授業の話などを、佐野コーチとはバックフリップの話などをした。) 先日(2月8日)行った時にはリンクはガランとして、コーチの姿も2,3人と少なかった。多分バンクーバーに行ってしまったものと思われた。 余段(バンクーバー・オリンピックのフィギュア雑言) バンクーバー・オリンピックのフィギュア日本代表は、厳しい選考会を勝ち抜いた選手達である。 男子では高橋大輔、織田信成、小塚崇彦、女子では安藤美姫、浅田真央、鈴木明子である。 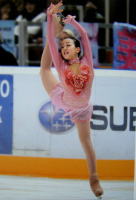 特に浅田真央は韓国のキム・ヨナと長年のライバル関係にあり、お互いにデビュー当時から身長が伸び、ダイナミックになった分、スケーティング技術で困難な課題を克服したものと思われる。 特に浅田真央は韓国のキム・ヨナと長年のライバル関係にあり、お互いにデビュー当時から身長が伸び、ダイナミックになった分、スケーティング技術で困難な課題を克服したものと思われる。 キム・ヨナのスピードの乗った迫力あるスケーティングと高いジャンプ、浅田真央の優雅で柔軟性ある天才的なスケーティングと3回転半のトリプルアクセル、ほんの少しのミスによる勝負になりそうである。 キム・ヨナのスピードの乗った迫力あるスケーティングと高いジャンプ、浅田真央の優雅で柔軟性ある天才的なスケーティングと3回転半のトリプルアクセル、ほんの少しのミスによる勝負になりそうである。毎日新聞社「バンクーバーオリンピック・フィギュアスケート完全ガイド」によると、2人の特徴的なスケーティングの差には、技術的に使用しているブレードに大きな違いがある、とされる。 キム・ヨナの使用している「ゴールドシール」はエッジが流線型で、深いエッジワークが可能で、スピードに有利とされ、浅田真央が使用する「パターン99」はトウが大きくジャンプには有利であるが、スピードには不利とされている。浅田真央の場合は天才的な滑りでスピードをカバーしている、という。 09年10月のジャパンオープンで浅田真央はトリプルアクセルでミスをしたが、氷が柔らかく、エッジが氷にはまって高さが出なかったため、とされる。 2月のバンクーバーでは氷も硬いことが予想され、通常エッジの溝のrは21mmφであるが、19mmφの砥石も用意するという。世紀の対決は間近である。 |
| 平成22年2月 |